◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇
今年は「敬老の日」が9月15日になりました。幼いころから「敬老の日」は9月15日だと記憶して育ったものですから、毎年日が変わるようになってからは、この日が軽くなったように感じるようになっていました。幼い頃、その日は祖父母へのプレゼントを毎年いろいろ考えて、「今年はどんな誉め言葉を…」と期待して迎えたものでした。父母が"還暦"を迎えてからも「母の日」「父の日」を続け、「敬老の日」の催しは子たちに譲りました。
2002年までは「敬老の日」は毎年9月15日でした。2003年(平成15年)から、9月の第3月曜日となり、年ごとに日付けが変わるようになりました。祝日の一部を月曜日に移動させる「ハッピーマンデー制度」によるものですが。この「ハッピーマンデー制度」は、「成人の日」「体育の日」「海の日」なんかにも変更を来たし、"何故この日なのか"と言う「意義」が見えなくなってしまったのではないでしょうか。「ハッピーマンデー」とは、祝日の一部を月曜日に移動させ、土曜日、日曜日と合わせて3連休とすること。祝日法の改正により、2000(平成12)年に移動が決まりました。(観光業界からの提案とか、と聴いていますが。)
この「ハッピーマンデー」を喜んでいた時代の私もいました。しかし雇用労働者を離れて経営者になってからは、悩みになっていました。業種が主としてイベントを核にする業務が多かったからです。シフトが利かない超零細企業でしたから…。学生アルバイトには助けられました。
今は多様な働き方ができる時代になっています。正社員でも"スキマバイト"は、労働者が自分の働きたい時間帯に短時間の単発の仕事をするという労働形態で、日常の中で発生する隙間のような時間にアルバイトをすることに由来した名で、スポットワークとも呼ばれています(多くはスマートフォンのアプリを使用することで、労働者と企業をつないでいる)。労働者はアプリで希望などが検索できる時代です。終身雇用制度で縛られない働き方ができますが、そのアプリの信用性が問われています(トクリュウとか)が。
高齢期に必要なのは、「社会と繋がっていること」と言われています。リタイア後、どのようなネットワークに属しますか? 「趣味の同好会」「同窓会」「学校・会社の同期会」「地域文化研究会」「地域ボランティア」「旧ママ友・旧パパ友」…。リタイア後、自己の存在をどこに置きますか? 私は早朝ウォーキングの知人・仲間たちですが。
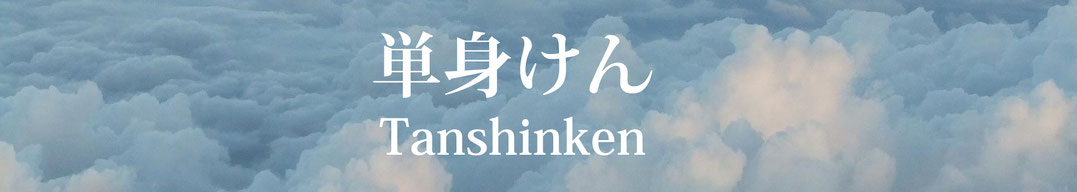
コメントをお書きください