◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇
「旧盆」と呼ばれている8月13日から16日が終わりました。毎夏この前後の時期は"帰省シーズン"と呼ばれていますが、実父母・義父母を送ってからは、お墓参りのときとなり、同居家族を亡くしてからは、供養行事の期間となりました。先代から習い継いだ"接待供養"からは随分簡略化していますが、気持ちだけは汲んで欲しいと思って過ごしました。あなたの地域の「お盆」は7月ですか? 旧暦でしょうか?
今年の「旧盆」を挟んだ期間の報道は太平洋戦争関連が多く「戦後80年特集」が占めていました。例年は「おばあちゃんちへ行ってきた」という子供のインタビューシーンが駅頭から送られてくるのが定番でしたが、「戦後80年特番」として長時間、また、シリーズで多様に放映されていました。
番組をチラチラ視していて思ったのは、「経験談を語れる世代が少なくなる中、悲痛な戦争の記憶の継承をいかにして続けていくかが重要」と「不戦に対する決然たる誓いを、世代を超えて継承すること」が、インタビューを受けた方からの言葉の大半でした。
今も世界各地で戦争状態が続いています。「経験談を語れる世代が少なくなっている」とは思いますが、戦後育ちでも"戦争を知らない"訳ではないでしょう。私は1944年生まれなので、同級生には"戦災孤児""戦災遺児""戦争未亡人の母の子""傷痍軍人の父の子"がいらっしゃいました。2010年、「高齢者」と呼ばれるようになる年に高校の同期会の有志で「私の戦後」という文集を発行しました。その時まで各自の生い立ちや育ちの生活環境を知らずにお付き合いをしてきていました。児童・生徒として、同期の仲間として。
戦後育ちの私たちですが、戦争の理不尽さや悲惨さ等々は、国内外の映画やテレビ、出版物でずーと見聞きしてきています。今年の総理談話で「大戦に対する『反省』」の語句を13年ぶりに使われたそうですが、「反省」の中身は伝えられていなかったように思うのですが…。「大東亜共栄圏」というスローガンの下、領土や資源を「武力」で略奪しに行ったのがあの大戦でなかったのでしょうか。ロシアは今黒海の良港を武力で略奪しに行っています。露国は黒海から地中海へ出る港を確保するのが何百年も前からの念願という風に長年聞いていますが。
この件に関して近々EUなど主要国の首脳会議が持たれるような報道が今日ありましたが、「武力」に依らず、ロシアが黒海に船を出すことができる道もあるのではと思う、極東の国の後期高齢者の婆さんは独りごちています。
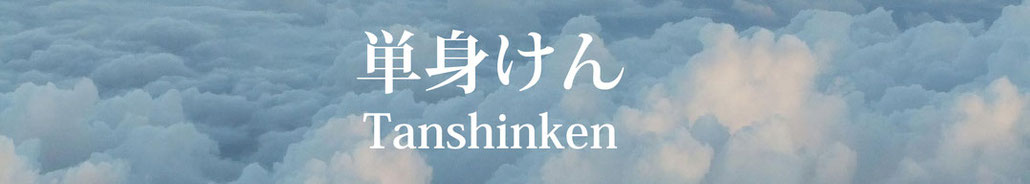
コメントをお書きください