◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇
7月の定例会は19日。3連休の初日で参院選の前日、おまけに猛暑の午後。テーマは「こんなサポート事業があったらいいな、を出し合いませんか?」でした。
参加者が3人という寂しさのせいかもしれませんが、個人的な"おしゃべり会"になってしまいました。でも、高齢者3人の話は"終活"の進み具合になり、エンディングノートの記入・断捨離など、進んでいるようで進んでいない私や、40歳から始めていたというAさん、着々と進めているらしいBさん。最後はテーマに沿っていました。
Aさんは40代から始めていたと言い、献体や女性のための埋葬施設に早々と契約したという堅実派。賃貸住宅で暮らしているので、死亡時の届も親族でなくてもOK。また、住宅等不動産の処理の心配も不要。緊急連絡先は単身けんの「緊急連絡先お預かりサービス」に登録してあるので、親族に連絡が行くという。素晴らしい! ところが何十年も経つと、高齢になったきょうだいは居なくなり、甥や姪は疎遠になり、緊急連絡先から連絡が行っても死後事務ができないかもしれない事態が生じてきたとか。せっかく早くから心がけて準備してきた「計画」が実行されない可能性が出てきたと言います。
NHKは6月21日スタートのドラマ「ひとりでしにたい」を事例に、一人暮らしの中年期の人たちへの"終活"を促す報道番組をいくつも放映しています。この報道番組は参考になりますが、私から言えばいくつか気になることがあります。特に、せっかく築き上げた"終活指示書"を実行してくれる人に誰が届けてくれるか、です。Aさんのように「緊急連絡先」と契約していれば届くでしょう。その実行役が経年と共にそれが難しくなってくることもあります。若いうちから"終活指示書"を作っておくのは大賛成ですが、その"終活指示書"の中身も変わってきます。
一番変わってきているのが家族の在り方です。単身世帯の増加です。特に都市部では、単身世帯は15歳から64歳までの現役世代の割合が多く、現役世代の単身世帯は東京で75.5%。神奈川69.0% 千葉67.0%・埼玉でも65.9%(2020年国勢調査より)とか。
このような現状から、自治体も「終身サポート事業」を立ち上げ始めています。現時点で15市が実施しています。都市部は現役世代の割合が多いことでしょうが、過疎化地域では高齢の方が多く、その担い手も少ないことでしょう。定例会では、この事業「就活情報登録伝達事業(わたしの終活登録)」を2018年5月、最初に開設した神奈川県横須賀市の事例を見てみました。登録は横須賀市民であれば可能で無料です。同市は親族などの求めに応じて、事前に登録された情報を開示すると言います。このようなサービスがあれば、死亡届を出せば"終活指示書"が親族等に手渡されます。このようなシステムがユニバーサルサービスになれば、と願う私です。
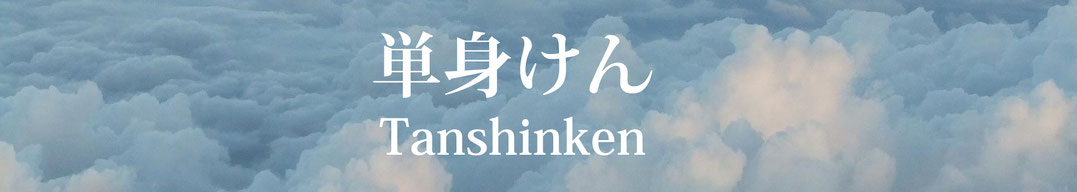
コメントをお書きください