◇事務局・石川由紀が折々を綴っています。◇
今年は選挙の年と言われています。4月末までに9地方自治体の首長選挙がありました。5月以降では15の地方自治体の首長選挙が予定されていて、7月には参議院議員選挙(投票日予定7月20日)、東京都議選の投開票日は6月22日だそうです。
希望が持てる年度になることを願っています。しかし、テレビの国会中継や新聞報道を視聴していると、国会議員は国レベルの議論ではなく、地方自治体の議会が果たすべき課題のような議案や議員個人の行動への口撃が多いと思いませんか?
国民生活のことと言いながら、全国一律に補助金や支援金を提案する国会議員。各地方自治体の住民の生活資金の困窮度の原因は各地方それぞれなのですが…。例えば"少子化対策"の教育費。義務教育の授業経費や学習資材は基本的に全国的には差が無いかもしれませんが、過疎化が心配されている地方では、通学の交通費、また義務教育(小中学校)外の教育を受ける場合は下宿生活費等などのかなりハードな出費が必要です。
高齢期生活に於いても、消費者が少ない地方では医療も介護も、買い物や移動手段もビジネスとして成立しにくいですから、企業等の撤退が生じるのはやむをえないのでは? その結果、過密市町村の住民との生活費の差はかなり大きく膨らみます。
このように考えていると、ユニバーサルサービスを論じる時、地方自治体の政治家が各地域の需給を勘案して、支援策や支援金・補助金を算出し、政策を提案し、当該自治体で不足する分は地方交付金等の請求を地方自治体から国にする等の行動をすることが大切なのではないかと思うのですが…。地方議員と国会議員では役割は異なるのでは?
「今春の賃上げ要求はかなり成果を見たが、生活諸経費の価格が高騰しているから、消費税を撤廃して家計を助けようとの議論が各政党から出ている」との報道が多くなってきています。1昨日は野菜や米など食品価格の高騰を危惧して、食品に対する消費税の撤廃を政策に掲げると発表した党がありました。それも1年限りの! コレって党としての7月の参議院議員選挙対策ではないのですか、と思った私です。
食費に困窮している家庭には"スズメの涙"程度の恩恵ではないのでしょうか? 好みの食材を価格など気にしないで購入している層の家計には大いに恩恵があると思います。これでは可処分所得の格差が益々広がるのでは…。マスコミは政党単位の評論を展開していますが、国民の日常生活は地域の特質・環境の中で行われています。選挙って党に票を入れるのではなく、立候補者個人に投票するはずですよねぇ。投票するのは一人だけ。誰に…。
参議院選挙まで3か月を切りました。各党からはどんな妙案が出て来るか! 楽しみです。
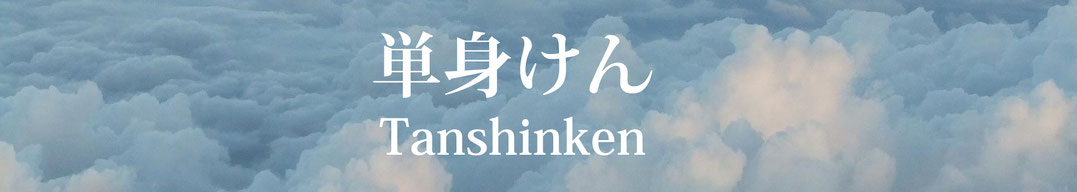
コメントをお書きください